第二話 九歴 弥生
016 弥生姉
「Xくん、これなんかどうかな?」
「ダメですよ、社長。見た目より機能性重視です。命を預かるんですから」
「そ、そうだよね。命の方が大事だもんね」
卯月はXくんと買い出しに来ていた。
通常の大手クエスト・ガイド・オフィスは専用の職人を抱えているのだが、卯月の会社の様な小さな会社は職人の数に対して、見合うだけのクエスト・ガイドがいないため、開拓冒険などで必要なアイテムは一般のアイテムショップなどで買い揃えていた。
一般のアイテムショップになると職人の質も多少なりとも落ちてしまうので、どうしても、良いアイテムとそうでないアイテムを見分ける観察眼が必要になっていた。
ろくでもないアイテムを手にしてしまうと冒険の時には命に関わるので、慎重なアイテム選びを必要としていた。
アイテムショップの雰囲気としてはホームセンター等が近いだろう。
ただし、アイテムには作った職人の顔も見える様に、売り場毎に、作った職人の顔写真が貼ってあった。
「お、あった、あった、社長、この職人は良い仕事をしますよ」
「へぇ〜そーなんだ?」
冒険家としてのキャリアがあるXくんは良い職人の顔はある程度、覚えている。
それをあてに二人で買い出しに来ていたのだ。
「あら、卯月じゃない?どうしたの、こんな所で?」
卯月は突然、声をかけられる。
卯月の三番目の姉、九歴 弥生(くれき やよい)だった。
「弥生姉こそ、どうしてここに?」
「決まってるじゃない。ミスターグッズのアイテムを買いに来たのよ」
ミスターグッズとはXくんもさがしていたアイテムを作った職人の事だ。
彼は特定のクエスト・ガイド・オフィスと専属契約は結んでいない。
一般の冒険者達にも自身の作ったアイテムを提供しようとアイテムショップでのみ、販売しているのだ。
「さすがですね、弥生さん、僕らも彼のアイテムを探しに来たんですよ」
Xくんが弥生を褒める。
弥生の時の審査官も彼が勤めているから顔見知りでもあった。
「むっ」
卯月はちょっと不機嫌になる。
彼女はあんまり、Xくんに褒められる事がない。
たまたま会った弥生があっさりと褒められたのが面白くないのだ。
「X様もですかぁ♥、気が合いますね私達♥」
鈍い卯月と違って、弥生はあっさりXくんの正体に気づいていた。
気づいていた上で、正体を隠しているのには理由があると察し、Xくんという名前で通しているのだ。
「や、弥生姉は何を買ったの?」
卯月がXくんと弥生の間に割って入る。
仲良くしているのが面白くないのだ。
「何、あんた?ひょっとして、私がX様を引き抜くんじゃないかと思って警戒しているの?」
「ち、違うもんっ」
違うと言いながらも顔は正直で、焦っているのが丸わかりだった。
「舐めないでね、私は無理矢理引き抜こうなんて無粋な真似はしないわよ。正式に申し込むわよ。その時は」
「な、なら、良いけど……」
「じゃあ、私、こっちだから――X様、また、お会いしましょう」
「あぁ、はい。そうですね」
「ではごきげんよう」
そういうと、弥生は奥の方に消えて行った。
「どうしたんですか?お姉さんと会ったのに何だか不機嫌そうですけど」
「なんでもない」
「なら、良いんですけど」
Xくんは首を傾げた。
017 ミスターグッズのアイテム
「うーん、これと、これと、これが欲しいところだけど、予算が……」
Xくんは悩んだ。
良心的な価格で定評のあるミスターグッズのアイテムだが、長期間の冒険に耐えられるような良質の物となると、多少、値がはるのは仕方がないことでもあった。
近場の冒険の依頼は比較的あるが、それだと、危険とは無縁のバカンス的な冒険となる。
そうなると、やはり、多くの報酬は請求出来ない。
それでも、数をこなせば、それなりに収益にはなるが、従業員が、卯月とXくんだけなので、手分けをしても大した金額にはならない。
経営の事を考えると、やはり、少し遠くの危険地帯への冒険案内も視野に入れないと行けないが、現在の装備だと心もとないのだ。
だから、せめて、いくつかだけでも良い物を装備して、冒険に出たい所だけど、懐の方が寂しい状態になっている。
父、師走に泣きつくかとも思うが、父には二人だけで会社を運営出来るという所を示したいので、その選択は最後の最後の手段として考えている。
ミスターグッズ以外の職人を選択すれば買えるが、よく解らない職人の作ったアイテムに命を預けるのはちょっと怖い。
だから、どうしても欲しいのだが、買ってしまうと、食費を削る事になる。
食費を削るのは体力勝負のクエスト・ガイドにとっては危険を伴う。
食事は取れる時に取って、しっかり体力をつけておくのはクエスト・ガイドにとっては必須の条件とも言える。
ならば、どうするか?
それを考えていた。
「お金、足りないの?貸そうか?」
と、声をかけてきたのは先ほど、別れた弥生だった。
彼女は買いたいアイテムを無事に見つけ戻ってきたのだ。
「本当ですか、弥生さん?」
Xくんとしては嬉しい提案ではある。
だが、卯月としては……
「条件があるんでしょ?」
だった。
「まぁね。タダでという訳にはいかないわね。こっちも商売だし」
弥生はすました顔でそう言った。
「な、何、条件って?」
「X様を引き抜きたいわ」
「何、言ってんのよ。そしたら私、一人になっちゃうじゃない」
「そうね。だから、トレードしましょ。私の方は10人、クエスト・ガイドを出すわ。みんな優秀よ。X様にはそれくらいの人数と交代しないと釣り合わないからね」
「やだやだやだ。嫌だよ、そんなの」
「もちろん、それだけじゃないわ。このアイテムショップに売っているミスターグッズのアイテム全てが買えるくらいのお金も無償提供するわ。どう?、良い話でしょ」
「どこが、Xくんは渡さないもん」
「X様はあんたのものじゃないでしょ」
「うちの社員だもん」
「なら、この話は無しね」
「ぐぬぬぬぬ……」
「品の欠片もないわね、それ」
卯月は歯噛みし、それを下品と評する弥生。
姉妹喧嘩は止めて欲しいと思わず、ため息がでるXくんだが、
「ここはどうだろう、弥生さん。君が提案する勝負をして、勝ったら、報償をいただくと言うのは?もちろん、うちが負けたら対価を支払うよ」
「X様がそうおっしゃられるなら、私としてはそれでもかまいませんわ」
「うちとして欲しいのは三つ、スキルコピードールとアーステント、スカイエスケープなんだ。それに見合った条件を出して欲しい」
Xくんは弥生に三つのアイテムを請求した。
まず、スキルコピードールはクエスト・ガイドのスキルをある程度、コピー出来る人形の事だ。
社員が卯月とXくんだけでは、どうしても人数が心もとない。
理由は冒険案内等をしている間は冒険希望者の対応が取れない事だ。
どうしても、効率が悪くなってしまう。
なので、せめて事務スタッフなどを雇うかしたいところだが、今はあまりその余裕が無い。
ならば、どうするか?
一人が冒険に出て、もう一人が冒険の募集の受け入れをすると言う事になる。
そこで役に立つのがスキルコピードールだ。
本人がいけなくてもスキルコピードールにいけない方の情報を入力しておくことで、ある程度の代わりになる。
一般用のスキルコピードールはせいぜい体術程度のコピーが関の山だが、ミスターグッズのスキルコピードールは三回以上のマジックスキルコピーも可能になっている。
さらに、使われている魔法石の純度も比較的高い。
お買い得中のお買い得という感じになっている。
これは是非とも手に入れたいところだ。
次に、アーステントだが、遠方の冒険になると、やはり安全地帯での睡眠も必要となる。
事前に確保出来ればそれに越したことはないのだが、無理な場合は地中にテントを張ってやり過ごすのが比較的安全策と言える。
アーステントは地中にテントを張ってくれるアイテムなので、是非とも手に入れたいアイテムだ。
通常のアーステントは一回限りの使い捨てだが、ミスターグッズのアーステントは大事に使えば、10回は使用できるように頑丈にできている。
最後はスカイエスケープだが、緊急脱出装置になる。
命の危険にさらされる危険に見舞われた時、空中に脱出するものだ。
とは言っても、空を飛ぶ敵に対してはあまり意味がないが、ミスターグッズのスカイエスケープはステルス機能も搭載しているので、そのあたりはありがたい機能と言える。
冒険としては危険を伴う遠方を選択したいので、最低限、これだけは手に入れておきたかった。
018 弥生の出した条件
Xくんの希望に対して弥生が提示した条件は、
「そうねぇ、その三つを提供する条件としてはうちのCクラスのクエスト・ガイドと勝負して勝てたら差し上げても良いわ。賞金も出すからそれで事務くらい雇えるようになるわよ」
だった。
弥生の会社、【弥生クエストカンパニー】にはクエスト・ガイドが弥生本人も含めて百人以上在籍している。
姉妹の中ではこれは長女、睦月の会社に次いで二番目の大所帯だ。
総勢、129名からなるクエスト・ガイドは能力により四つのランクに分けられている。
頂点をSランクとして、続いてAからCまでとなっている。
弥生としてはCランクを鍛えて、所属するクエスト・ガイドの底上げをしたいのだ。
目標としてはCランク全員をBランク以上に上げて、Cランクは在籍していない状態にしたかった。
基準を高めにしているので、Cランクと言ってもクエスト・ガイドのレベルは高いのだが、最低ランクという事になってしまっているので、最近、やる気というものが落ちてきているのではないかと心配になっていた。
卯月と勝負をさせて、発破をかけるのも良いかな?とちらっと思ったのだ。
幸い、Xくんの指定した三つのアイテムは【弥生クエストカンパニー】にとってみれば、大した失費ではない。
クエスト・ガイドのスキルアップにかける費用を考えれば、安いものだった。
卯月が負ければ、Xくんを週に一度、出向させるという条件をつければ、弥生としては全く文句のない条件だった。
「うーん……」
卯月は悩んだ。
負けたら一週間の内、一日はXくん無しで営業しなくてはならないのだ。
「社長、勝てばいいんですよ、勝てば」
Xくんがにっこり笑う。
弥生にはプライドがある。
姑息な手段は使わない子だ。
正々堂々とやってくるだろう。
後は勝てば良い。
Xくんは弥生の事をそう評価している。
卯月、弥生に限らず、九歴家の姉妹達には誠実たれとXくんは常に言っていた。
それを違えるとは彼には思えなかったのだ。
人間、誠実なだけではやってはいけない。
だけど、根角の前では彼女たちは常に誠実だったのだ。
Xくんはそれを信じていた。
Xくんが言うなら、信じてみようと思った卯月は、
「解った。受けるよ、弥生姉、この勝負」
といった。
弥生はにっこり笑い、
「そう、じゃあ、その三つはうちの方で買わせてもらうわね。あんたが買ったら、さしあげるわ」
と告げた。
019 Cランク クエスト・ガイド
「社長、深呼吸して」
緊張でガッチガチの卯月をXくんはリラックスさせようとしていた。
今日、彼は、だるまのマスクをしている。
一体、何種類のマスクを持っているのだろう?
彼は、正体を隠すマスクをおしゃれの一つとしているのかも知れない。
「そ、そんなこと言ったって、他のクエスト・ガイドの人との試合なんて始めてで──」
「【弥生クエストカンパニー】のクエスト・ガイドはやる気が少し低下していると聞いています。何が何でもアイテムが欲しいうちとはやる気の点でまるで違います。活路はそこにあると思いますよ」
「何が何でもって……」
「あのアイテムがあると無いとではうちの経営は全く変わって来ます。死活問題と言っても過言ではありません。緊張しているあなたにその事をあえて伝えたのは、緊迫感を持ってもらうためです。クエスト・ガイドとは緊張感の連続の職業でもあります。開拓冒険の時のあなたは緊張感が足りないように思いました。この機会に緊張するという事に慣れてくださいね」
「えぇ〜」
「えーじゃありません。会社を背負っているんですから、もう少ししっかりしてください」
「う、うん。わかった」
「よろしい。じゃあ、ルールを確認します」
Xくんは弥生から提示された今回の勝負のルールを書かれた紙を見せた。
ルールとしてはアイテム1点につき、一人のクエスト・ガイドと勝負するというものだ。
三つのアイテムが欲しい、卯月としては三人のクエスト・ガイドと勝負して全勝しなくてはならない。
一敗でもすれば、Xくんを貸し出す事になってしまう。
例え初戦で負けても、次の試合をすることも出来るが、二敗したら二日、三敗したら三日、Xくんを貸し出すという事になる。
それは、冗談ではない。
一敗もしたくないというのが卯月の本音だ。
だが、相手はCランクとは言え、大手のクエスト・ガイドだ。
経験は卯月よりずっと上なのだ。
楽に勝てる相手ではない。
初戦は花巻 栞(はなまき しおり)、
二戦目は黒羽 聡美(くろばね さとみ)、
三戦目はリタ・ウェーバー。
三名とも遠方冒険回数十回を超える経験を積んでいる。
まともな遠方冒険は一度もない卯月よりスキルは数段上という事も考えられる。
認定試験では才能の高さを発揮した卯月だが、実戦に勝るスキルアップはない。
才能はともかく、実力は相手の方が上と思った方が良いだろう。
ただ、栞との勝負は組み手、聡美との勝負はアスレチックレース、リタとの勝負はスピードのあるモンスターを想定した回避術勝負。
これはそれぞれのクエスト・ガイドがBランクに上がるために必要な、彼女達が苦手とする種目での勝負だと推測出来る。
社長の弥生は苦手分野の克服をさせたいと思っているだろうからだ。
そこに、卯月のつけいる隙間があると言える。
「社長、あれこれ考えても仕方ありません。勝つときは勝つ、負ける時は負けるんです。今回は死ぬような危険のあるものではありません。あなたの好きなガッと行って来て下さい」
「えぇ〜、アドバイスって、それ?」
「僕も賭けの対象となっている以上、これ以上、助言するのはフェアではありません。信じてますよ。ガンバってきてください」
「そんな事言われたって……」
「貴女の欠点はあまり考えない事ですが、それは逆に長所でもあります」
「え?え?どういうこと?」
「ガンバってください」
「いや、そうじゃなくてどういう意味」
「余計なことを考えなければ何とかなるという事です。じゃ、僕はこれで」
「ちょちょちょ、ちょっと待って」
その場を立ち去ろうとするXくんを呼び止めようとする卯月に対して、
「ちょっと、何やってんのよ、卯月、こっちは暇じゃないんだから、早くして」
と弥生からの催促があった。
「わ、わかったってば」
卯月は渋々、試合をする事にした。
020 花巻 栞との勝負
「社長〜頑張って」
「え、Xくん、応援は良いから何かアドバイスを」
「ファイト」
「だから、アドバイスを」
「そこ、私語うるさい」
卯月はXくんにアドバイスを求めるが、Xくんは応援だけで、何も言ってくれない。
オマケに、弥生に注意されてしまった。
誰にも頼れない。
そんな状況だった。
だが、Xくんは考え無しにやっている訳ではなかった。
この先、Xくんがべったり、卯月との冒険に付き添っていく訳にはいかない。
それでは、いつまでたっても彼女は成長しないからだ。
自分で考えて、自分で行動する。
自分が開拓して来た、新しい土地の情報を自分の言葉で冒険者に伝えなくてはならないのだ。
それが、クエスト・ガイドという職業だからだ。
何から何まで、Xくんが答えていたのでは、卯月自身のクエスト・ガイドという職業は成立しないのだ。
遠方の冒険をするようになれば、それは確実に、増えてくる。
だから、遠方への冒険の前にたたき直す必要があったのだ。
なので、卯月にとっても弥生の会社との勝負は願ってもない状況なのだ。
そんな彼の思惑を知ってか知らずか、
「お、お手やわらかにね、お願いね」
と弱気な態度だった。
「栞、負けたら補習だからね」
弥生はCランクのクエスト・ガイドに檄を飛ばす。
「この人、社長の妹さんですよね?本当に姉妹ですか?何か随分、頼りない感じがするんですけど?」
栞は舐めていた。
完全に卯月を見下していた。
「腐っても私の妹よ。油断しない」
「弥生姉、腐っているは酷い」
「そんな、へっぴり腰をしている内は十分腐っているわよ」
「さすが、弥生さんですね。僕もその通りだと思います」
「Xくん、どっちの見方なのぉ〜?」
「だから、立場上、どちらの見方もできませんよ」
「ひーん」
「無駄口はそこまで、始めるわよ。双方、良いわね」
「オッケーで〜す、社長。ぱぱっといきまぁ〜す」
「こ、こっちもオッケー……」
「始め」
弥生がレフェリーとなって組み手の試合が開始された。
この勝負は先に五本、決定打を打ち込んだ方が勝ちという勝負だ。
ヒュッ
「はい、まず、いっぽ……」
んと言おうとした栞だったが、偶然か、滑った卯月の一撃がたまたま、先にヒットして、栞の攻撃は無効になった。
「や、やった……」
「ちっ、まぐれ当たりか」
今の一撃を卯月と栞は、たまたま決まった偶然と判断したが、Xくんと弥生は別だった。
「栞、本気でやりなさい。このままだと、あんた、負けるわよ」
「何、言ってんですか、社長、たまたまですよ、たまたま。一発入っただけじゃないですか、これからですって」
「悪い癖が出た。補習決定ね」
余裕顔の栞に対し、弥生は苦虫を噛みつぶしたような表情になった。
そして、弥生の考えは的中する。
一本くらい大した事ないと思っていた栞だが、二本目、三本目と入れられていく内に、余裕が無くなり、慌てて三本取り返した。
三対三の同点となった栞は
「追いつこうと思ったら、余裕なのよ、あんたなんか」
と強がりを言った。
「バカ、これが死闘なら一本目の時、栞、あんたの方がやられてたのよ」
「もう、一本もやらせない」
気合いを入れ直す栞だが、卯月の方は三本入れられた事により、余裕が持てた。
その後、二本卯月が連取して、この勝負は卯月の勝利となった。
「な、なんで……?」
「先に、卯月の方が冷静になれた。敗因は増長して、それが遅れたことよ」
「そ、そんな……」
卯月の一勝目だった。
だが、これは相手が油断していたから出来た事。
次はそう簡単にはいかない事でもあった。
021 黒羽 聡美との勝負
次の聡美との勝負はアスレチックレースだ。
身体の大きな聡美は小回りが利かない。
なので、それを鍛えるための勝負でもあった。
これは勇者教育センターの巨大体育館で行われる。
設定条件としては冒険者が傷を負ってしまって、そこから離脱しなくてはならない状況という事になっている。
なので、卯月と聡美は50キロの重りを持ってでの勝負となる。
もちろん、50キロの重りをつけて俊敏に動けるような事は無い。
そのため、サポートアイテムの使用が認められる。
スタートして100メートル重りを引きずって行ったところに、アイテムが10種類おいてある。
走者はどのアイテムを使っても良いが、次のポイントまでそのアイテムを駆使して、進むことになる。
次のポイントでは5種類、5つ、その次のポイントでは3種類、3つ、最後のポイントでは1種類2つのアイテムが用意されていて、そのどちらか片方は故障している。
最後のポイントでは正確に動くのはどちらかという事を見極める観察眼も必要になるし、故障していた場合、応急措置をして、それを上手く利用する発想力も求められる。
それぞれのポイントに置いてあるアイテムの説明はされていない。
なので、あらかじめ頭の中に予備知識が必要とされる。
知力、体力を必要とする勝負なのだ。
「双方、準備は良いわね、レディー……」
パァン
銃声と共に、50キロの重りを引きずって、最初のポイントに向かっていく卯月と聡美。
小回りが利かなくても、その分、身体の大きさから、体力は卯月よりもある聡美の方が、やはり、先に最初のポイントにたどり着いた。
どれを使うか悩んでいたが、その中の一つを選択し、次のポイントまで動き出した。
彼女が選択したアイテムは、魔法薬グラビティーの元だ。
これは重力操作の魔法に必要な薬で、振りかけると多少物の重さを軽くすることが出来る。
彼女はこれに倍化の魔法を付与し、50キロの重りを5キロの重りに変えて運んだのだ。
重さが十分の一になることで、彼女の運搬スピードは跳ね上がった。
続く、卯月が選択したのは、梃子(てこ)の木片だ。
これは梃子の原理を応用したアイテムで、不思議と軽く感じるという便利グッズだ。
勉強はたくさんしてきた卯月だが、実戦で使った経験が無かったので、勉強で覚えたもの中でイメージしやすいものを選択した。
そうこうしている内に、聡美は次のポイントにたどり着いた。
魔法薬グラビティーの元はリセットされ、次のアイテムを選択する事になる。
次に選択したのは機械獣プロペラだ。
機械仕掛けのロボットの名称で、荷物運びに適している。
だが、自動で運ぶので聡美自身との連携が取れない。
勝手に運んでくれるので、聡美自身は楽だが、スピードが出ない。
その隙に、このコースは障害物が少ないと判断した卯月が自転ソリに乗せて運んで、ほぼ、並んだ。
次のポイントでは同時スタートで、卯月は簡易転送装置、聡美はスキルコピードールを選択する。
スキルコピードールに聡美は情報を入力して、協力して、重りを運ぶ。
一方、卯月は簡易転送装置を配置していく。
一度に転送出来る距離と重さが限られていて、50キロの場合はせいぜい、20メートルがせいぜいだ。
だが、簡易転送装置の重さは軽いので、20メートル毎に配置していけば、後は、簡易転送装置を作動して一気に次のポイントに進める。
卯月はポイント間を二往復することになるが、簡易転送装置を持ってでの二往復は大した事はない。
卯月は最後のポイントに先についた。
が、彼女が手にしたのは故障した方のアイテムだった。
「やりぃ、勝った」
聡美が叫ぶ。
横から、正常に稼働している方のアイテム、浮遊座席に重りを乗せて運んで行く。
が、勝負は卯月が勝った。
彼女は故障していた浮遊座席を以前のものより性能をアップさせて、修理したのだ。
そのため、ふわふわ浮いているので、大したスピードが出ない聡美の浮遊座席より、格段にスピードが出るようになり、抜き返したのだ。
「状況を見誤ったわね、聡美」
「……はい、社長、すみませんでした」
「非を認めるだけ、栞よりマシよ。よく頑張ったわね」
「次は負けません」
「……そう」
聡美は悔し涙を流した。
お互い、全力を出した、良い勝負だった。
022 リタ・ウェーバーとの勝負
「リタ、あんたが負けたら、うちの面子は丸つぶれよ。何とか、勝ちなさい」
「オーケー、シャチョー。ミーは負けないね」
なんとしても三連敗という屈辱は避けたい弥生はリタに檄を飛ばす。
リタとの勝負は回避術勝負だ。
攻撃してはいけない。
攻撃を避けなくてはならないのだ。
リタは回避術が不得意という訳ではない。
ただ、手が出てしまうのだ。
彼女は前職が女子プロボクサーだ。
避けるのもお手のものなのだ。
だが、避けている内に攻撃してしまう癖が抜けなかった。
避けている内につい熱くなって殴ってしまうのだ。
回避術なので、避け続けなくてはならない。
攻撃してしまうと大きな減点になってしまうのだ。
これを冒険に仮定すると、クエスト・ガイドなので、敵を倒さなくても別に良いのだ。
敵に攻撃してしまうと、敵がクエスト・ガイドを自身の敵と認識してしまう。
そうなると、敵との抗戦が始まってしまう。
なので、そうならないために避けるだけの技術も必要とされていた。
そのため、リタは、Bランク以上の実力がありながら、Cランクに甘んじることになっていたのだ。
彼女がBランクに昇格するためには、この悪い癖を直さないと行けなかった。
そのために組まれた勝負だった。
そして、これは、卯月にも言えることだった。
ボスキャラと戦う事が大好きな性格の彼女もまた、避けている内に攻撃を開始してしまう癖がありそうなタイプだった。
つまり、似たもの同士の勝負でもある。
勝負の回避術勝負は同時に同じ場所で行われる。
まず、障害物が多数置いてある体育館に双方、隠れる。
そこに、ドローンを三十機飛ばし、隠れている場所を探索させる。
ドローンに見つかった時点で、自動攻撃システムと自動追尾ボックスが起動する。
自動攻撃システムは建物に配置されていて、自動追尾ボックスは回転しながら、追尾してくる。
自動攻撃システムと自動追尾ボックスからは特殊インクの入った弾が発射され、それに当たるとポイントがマイナスされるというものだ。
自動攻撃システムは共通して、当たったら、一発につき、1点マイナスとなる。
自動追尾ボックスは六面体の全ての面から弾が出て、出ている面によってマイナスポイントが−1から−6ポイントになる。
発射された面によっては一挙に−6ポイントも削られることになる。
自動攻撃システムは全200カ所、自動追尾ボックスは100機配備されている。
体育館の大きさから考えて、いかに回避術が長けていようとこれらの猛攻撃を回避し続ける事は出来ない。
要は持ち点1000点をいかに、長く保持し、0点以下にしないかという事が重要となった。
つまり、最初にドローンに発見されてしまった方にはそれだけ早く、攻撃が始まるために圧倒的に不利となる。
敵から何処まで隠れていられるかも勝敗を分ける事になりうる事だった。
当然、インク攻撃に耐えられず、思わず、手を出してしまったら、大きな減点となる。
本来ならば、その時点で、失格なのだが、二人とも手を出しそうなので、一回あたり、−30点という事にした。
「へい、ユー、ミーは負けないね」
「こ、こっちこそ」
お互い闘志沸き立っていた。
「じゃあ、始めるから、隠れて。十分後に開始するわよ」
弥生が開始を宣言した。
卯月とリタはそれぞれ、隠れた。
が、自信があるのか、リタは手前の方に隠れた。
それでは、ドローンに早く見つかってしまう可能性が高い。
「ユーはこれまでの二戦で疲れているね。だから、これハンデね」
ウインクするリタ。
あくまでも正々堂々、叩き潰すという事なのだろう。
卯月としても望む所だった。
十分が経ち、ドローンが解き放たれた。
リタはわざと表に出て行き、ジャブで、ドローン一機を破壊した。
「これ、ハンデ、その二ね。二回戦ってたから、ハンデ二つね」
とまた、ウインクした。
先に出たのと、ドローン破壊での−30点は栞戦と聡美戦での分という事なのだろう。
「あのバカ、ドローンの弁償、うちでしないといけないじゃない」
弥生はため息をついた。
バカ正直な所が卯月とそっくりな所がリタの欠点でもあった。
スウェーでかわして行くリタ。
だが、さすがにハンデをつけすぎた。
集中砲火を浴び、みるみる点数を減らしていく。
その時――
バシュッ
「な、なんでヨ……」
卯月がリタを庇って、集中砲火を受けた。
みるみる卯月の点数も減っていく。
「ハンデ、貰いすぎたから、ちょっと返す」
卯月もウインクして見せた。
これで勝っても彼女は嬉しくないのだ。
「後悔するネ、きっと」
「しないよ。勝てば良いんだから」
「言うね」
集中砲火を浴び、どんどん点数を減らしていく二人。
勝ったのは、1点差で卯月だった。
かろうじて、リタが0点になるまで1点を守り通した。
勝敗を分けたのは正に運だった。
卯月が避けた弾が彼女が死角となって、リタに当たってしまったというだけだった。
どちらが勝って、どちらが負けてもおかしくない微妙な判定だった。
「ゴメンネ、シャチョー、負けちゃったヨ」
「良いわよ。それが、あんたの良いところだもんね。補習は受けてもらうわよ」
素直に負けを認めるリタにねぎらいの言葉を弥生はかけた。
負けこそはしたが、素晴らしい、人材を持っていると言えた。
「弥生姉……」
「しょうがないわね、今回は負けたわよ。でも、次はこんなに上手くいくとは思わないでね。いつかリベンジするから、その時はよろしく」
「う、うん……」
「じゃあ、とっとと、持っていってちょうだい。負けた以上、この三つはあんた達のもんだし、未練なんてないわよ。うちとしては大した傷手じゃないしね」
「へへっ、ありがとうね」
「お礼なんて良いわよ。これは勝負。敗者は勝者に代償を支払った。ただ、それだけの話よ」
「そうだね。じゃあ、遠慮なく……」
卯月は勝利の笑みを浮かべた。
023 ところで……
「ところであんた、どうするの?」
弥生は卯月に尋ねる。
「どうするって何が?」
卯月は首を傾げる。
弥生の言っている意味が解らなかったからだ。
「じゃあ、聞いてないってことか、仕方ないわね、教えてあげる」
弥生はやれやれと言った表情で、卯月に伝えた。
「えぇ〜っ、そんなの聞いてない」
「X様はご存じでしたよね?」
「えぇ、まぁ。だから、遠方の冒険が必須だと思って準備していたんですよ」
「Xくん、私、聞いてない」
「言いましたよ。ただ、上の空で、あまり聞いてなさそうだったので、先に準備だけ初めて後で再度、伝えようと思っていましたけど」
「き、緊急事態じゃない」
「緊急なのはいつものことじゃないですか」
「言ってよぉ〜」
「だから、言いましたって。見たいテレビがあるから後にしてと言っていたのはあなたじゃないですか」
「え?いつ?」
「一昨日の夜ですよ。だから、昨日、アイテムショップで買い物したんじゃないですか」
「どどど、どうしよう?」
「慌てても仕方有りません。クエスト・ガイドを育てている時間が無い以上、他から引き抜くか、技量のある人間を見つけるしかありません。そのためには、遠方の開拓冒険に出て、うちの魅力をアピールしないと来る者も来ませんからね。本当に死活問題なんですよ、今は」
「わー、どーしよー?」
「慌てないで下さいって」
卯月は動揺しまくった。
彼女が慌てる理由――
それは、国の法改正による、クエスト・ガイドオフィスの認定基準の変更だった。
これまでは、最低、一人居れば、経営としてなりたっていたが、A級とB級にクラス分けされることになったのだ。
A級と認定されるには、クエスト・ガイド6人以上、事務スタッフ4人以上が必要とされる。
それに満たない人数の場合は実績の有無を問わず、B級に格付けされる。
A級は一流、B級は二流というランク付けがされるため、その後の仕事にも影響する大きな事なのだ。
今回の勝負で、事務スタッフは稼げば雇えるようになるが、クエスト・ガイドはそうはいかない。
弥生は何もイジワルで、Xくんとのトレードを申し出た訳ではないのだ。
クエスト・ガイドが足りないから補充してあげるという意味でも申し出たのだ。
姉妹の中では卯月の他に、少数精鋭でやっている次女如月(きさらぎ)の会社もこれに当たるが、彼女の場合はA級B級にこだわっていない。
例え、B級でも役に立たないクエスト・ガイドを雇うよりは少数精鋭であるという事を優先させるという事で、同じく、弥生の申し出を断っている。
だが、卯月の会社はそうは行かない。
B級にランク付けされてしまったら、それこそお客さんが遠のく事になってしまうのだ。
この法律が制定されるまでは一年間の準備期間があるので、それまでにクエスト・ガイドと事務スタッフを4人ずつ用意しないといけないのだ。
卯月が慌てているのを見ていたリタは
「弥生シャチョー、ちょっと、いーですカ?」
と言って来た。
しばらく、弥生とリタは別室で相談して、戻って来た。
「卯月シャチョー、よろしくネ」
と突然、リタが言った。
「は?」
卯月は思わず聞き返す。
「えーとね、何から話したら良いのか、リタがうちを退職して、あんたんとこ入るってさ」
弥生が補足説明をした。
「本当ですか、リタさん」
Xくんが喜ぶ。
「卯月シャチョーのとこの方がスリルありそうネ」
リタがウインクする。
「ほ、ほんと?リタさん?」
卯月も後から喜ぶ。
これで、少なくとももう一人、クエスト・ガイドが増える事になる。
三人になれば、行動範囲もそれだけ、増える事になる。
「ほんとネ。ただし、会社潰れたら、弥生クエストカンパニーに戻るネ」
「も、もちろん、潰さないよ」
「なら、オーケーね。よろしくネ、お二人さん」
「こちらこそ、よろしくお願いします。歓迎しますよ、リタさん」
「ありがとう。本当にありがとう」
本当はXくんと二人きりというのをしばらく満喫したかったが、そうも言っていられない状況になったので、卯月と互角の実力を持つリタが加わってくれるなら頼もしい限りだった。
「全く、大損だわよ、こっちは。三連敗の上に優秀なクエスト・ガイドが一人、居なくなるんだから」
「弥生シャチョーには感謝してるネ。ユーがいなかったら、ミーはここまでせいちょーしなかったネ」
苦労はしたが、貴重な戦力も一人加わり、【卯月クエスト・オフィス】も良い走り出しをしていた。
後、クエスト・ガイド3人をどこかで、スカウトするのと事務スタッフ4人を雇う事。
それが、一年後までの絶対条件となった。
024 事務スタッフを雇おう
リタ・ウェーバーという強力なクエスト・ガイドが加わった【卯月クエスト・オフィス】だが、事務スタッフが居ないと、クエスト・ガイドがそれを行わなければならない。
卯月とリタはそういうタイプではないので、必然的にXくんが事務作業をやる事になる。
そのため、貴重な戦力であるXくんが事務メインの仕事を余儀なくされている状態なのだ。
これは宝の持ち腐れ状態と言える。
Xくんには、是非とも数多くの開拓冒険に参加してもらって、【卯月クエスト・オフィス】で案内できる冒険地を増やして行って欲しいところだ。
なので、まずは、事務スタッフを雇う事が必要不可欠となった。
いくつか小さな冒険案内をして事務スタッフを雇う余裕は出てきた。
事務スタッフはクエスト・ガイドとしての技量は必要ない。
事務作業をこなしてくれる力があれば事足りる。
だから、簡単な話だ。
そう、高をくくっていた。
だが、現実問題はそう甘くは無かった。
まず、クエスト・ガイドという職業自体がメジャーではないというのが一点だった。
クエスト・ガイドの事務スタッフとして活躍するよりも勇者達のマネージャーとして活躍した方がずっと脚光を浴びるからだ。
ボスを倒すという事が殆どない、クエスト・ガイドの事務スタッフになろうという人間はそう、多くは無いという現実がある。
それでも、新しい職場でやってみたいという者は必ずいるが、そういう人間はたいがい、大手のクエスト・ガイドオフィスに流れて行く。
弱小オフィスである【卯月クエスト・オフィス】に入ろうという物好きは早々いないのだ。
たまに、やってくる応募者は何も考えて無いか、する事がないので、仕方なく来たという連中ばかりだった。
命の危険もある仕事なので、いい加減な人間にその事務処理を任せる訳にもいかず、来た人間は全員不採用とせざるを得なかった。
命を預かる仕事である以上、誰でも良いという訳にもいかないのだ。
しかし、条件をつり上げれば、それだけ、応募者も減っていく。
これだと思える人間はまだ、一人も居なかった。
このまま、悪戯に面接だけ続けても一年間という期間はあっという間に進んで行ってしまう。
クエスト・ガイドは開拓冒険をして、たくさんの冒険者に案内をしてなんぼの商売だ。
面接だけをズルズルと続けていく訳にもいかなかった。
「こないね……これだと思う人」
「てきとーなので良いんじゃないですカ、それより、ミーは冒険に出たいネ」
「そうもいかないよリタさん。大事な事だから」
「うーん、こっち来たの、はやまったかな?」
「そんなこといわないでよ。何とかしたいとは思っているんだから」
「Xくんは何してるですカ?ここの所、見ないですガ?」
「しばらく留守にすると言って一週間かぁ〜、どうしたんだろうねぇ?」
連日の面接に疲れているのか卯月とリタはダラぁっとしていた。
「なんですか、二人とも、だらしない。せっかく、良い知らせを持って来たのに」
戻ってきたXくんが呆れた。
二人を残しておくと何も進展しないと思ったからだ。
「Xくんこそ、どこ行ってたのよ。心配したんだから」
「そーネ、心配したネ」
「もちろん、事務スタッフをスカウトしてきたんですよ。待っているだけじゃ埒があきませんでしたからね。こちらから出向いたんです。あなた方は何をしていたんですか?する事が無いならスキルアップに勤めていただいた方が良かったのに」
「えー、でも事務スタッフ優先だって、Xくんが」
「お二人にはあまり期待してないから鍛えていて下さいと言って出て行ったつもりですが?」
「悔しいから、二人で、事務スタッフ見つけようって事になって……」
「待っているだけじゃ、無理ですよ。こっちも動かないと」
「どこ行ってたですカ?」
「あちこちです。連れてきましたよ。精鋭スタッフを」
Xくんはにっこり笑った。
025 事務スタッフ
「さぁ、どうぞ」
Xくんに促されて現れたのは4人の男女だった。
「な、なんで、ユー達がここにいるネ?」
真っ先に声を上げたのはリタだった。
彼女の顔見知りが約二名、混じっていたのだ。
「フィアンセの行く所について行くのは当たり前じゃないカ」
四人の内、一人がリタの婚約者を名乗った。
「フィアンセ?」
卯月はリタを見た。
「ノーノーノー、フィアンセじゃないヨ、こいつが勝手に言っているだけネ」
「オー、つれないネ、リタ!それが、ベッドを共にした男に言う台詞かい?」
「子供の頃の話ネ」
男性とリタがもめる。
「まーまー、知らない人もいるから紹介だけさせて欲しいな」
Xくんがその場をおさめようとする。
それでも、しばらくギャーギャー言い合っていたが、何とか少し落ち着いてきた。
落ち着いてきたのを見はからって、Xくんは紹介を始めた。
始めは社長である卯月を4人に説明、次に、リタを説明した。
その後で、新しく入ってきた4人を紹介した。
まず、リタと言い合っていた男性の名前はブリット・ウェーバーという青年だ。
リタとは従兄弟同士という事になる。
ブリットはリタに惚れていて、リタが移籍したのを聞いて、ブリットも弥生の会社から移る事にしたのだ。
ブリットも元々、クエスト・ガイド志望で優秀な成績をおさめていたが、クエスト・ガイドとして致命的な欠点が発覚し、事務職への転向となったのだ。
その致命的な欠点とは血を見ると失神するという事だ。
危険と隣合わせのクエスト・ガイドに出血はつきもの。
その度に気絶していたのでは話にならないというものだ。
彼の試験も見ていたXくんは彼の優秀さも知っていたので、事務職として雇う事にしたのだ。
二人目の男性の名前はスティーブ・ウェーバーという青年だ。
ブリットの5つ上の兄という事になる。
なので、リタとは同じく、従兄弟同士という事になる。
スティーブは元、冒険者だった。
不注意からの事故で肩を壊し、冒険者としての道を断念する事になったのだ。
実は、弟のブリットのことを溺愛していて、リタとの婚約を認めていない。
更に、実はリタから好意を持たれているので、三角関係が成立している。
リタはスティーブが、スティーブはブリットが、ブリットはリタが大好きという図式だ。
今までは弥生の会社に冒険者を仲介するブローカーとしてやっていたが、弟が、リタを追うと知って、自分も事務職として、追ってきたのだ。
三人目は皆川 彰人(みながわ あきと)という見た目は少年の人物だ。
ただし、本物の彰人少年は既に故人となっている。
Xくんが冒険で助けに向かった時に出会った少年だったが、不慮の事故で死亡した。
が、両親のたっての希望で、肉体だけでも生かして欲しいとの要望があった。
その時、丁度、肉体が失われつつあったエンシェントドラゴンの魂を入れて蘇生させたのだ。
もちろん、中味は彰人少年ではないので、両親とは無関係になってしまったが、それでも一月に一度、会いに行くという条件で、エンシェントドラゴンは彰人少年の身体を使って行動する事が出来るようになっている。
力はあるので、せめて、クエスト・ガイドになりたいと希望しているが、肉体が未成年なので、肉体が18才に育つまでは事務職をしてもらうという事になっているのだ。
肉体的には未成年だが、知能の方は長い年月を生きて来ているので、特例として、卯月の会社で働く事を認めてもらったのだ。
4人目は紅一点、桜咲 真尋(さくらざき まひろ)は研究者でもある。
天才肌ではあるが人間関係が上手く行かず、研究所を転々としていたのをXくんがスカウトしたのだ。
会話が苦手で、誤解される事も多く、他の研究者から疎まれていた、彼女にとって、研究することは息をすることと同じくらい大事に思っていたのだが、研究する場所が無かった。
クエスト・ガイドオフィスはA級に認定されれば、研究所を一つ以上借りることが出来るようになるという条件を出したら、それまでは事務職でやると言ってくれたのだ。
4人とも一癖も二癖もありそうな面子ではあるが、こうして、事務職4人が揃った事になる。
真尋は足かけというような状態になるとは思うが、それでも当分は、事務業を任せる事が出来ると思われる。
後は、3人のクエスト・ガイドを雇えば、最低限、必要な人数は揃うことになるが、ここで、問題が一つ。
他のクエスト・ガイドを雇う程の余裕が今はないという事だ。
資金面で逼迫しているので、アイテムショップに買い物に行っていたのだ。
弥生との勝負やその後の小さい冒険案内で、事務職は雇えるようになったが、クエスト・ガイドを雇えるような資金的余裕はまだない。
いきなり必要な人数を雇えるような状況ではないということだ。
だとすれば、まずは、今いる、三人のクエスト・ガイドで、稼ぐしかない。
稼いで、他のクエスト・ガイドを雇える余裕を会社にもたらすしかないのだ。
そこで、卯月、Xくん、リタの三人による遠方の開拓冒険をして、遠方への冒険案内サービスを増やすという計画も発表された。
026 いざ、次の冒険へ
「おーう、リタ、ボクもついて行くネ」
「いらないでース。スティーブの方がいいネ」
「オレは行かないネ、ブリットが居れば十分ネ」
リタ、スティーブ、ブリットのトリオ漫才も大分、慣れてきた。
事務作業の引き継ぎ、下準備等に一月かかり、いよいよ、遠方への開拓冒険に出る事になる。
そして、A級になるための予備期間終了まで十一ヶ月を切っている。
今回は危険度が高いので、卯月のすぐ下の妹、皐月(さつき)の会社の開拓冒険チームと途中で合流することになっている。
だが、この開拓冒険が成功すると、皐月の会社との合同とは言え、十分、更に二人はクエスト・ガイドを雇うくらいの資金が入るという見積もりだ。
この情報を他のクエスト・ガイドオフィスに提供する事によって、クエスト・ガイドとしての仕事の幅が、企業全体で伸びる可能性があるからだ。
それだけ、危険な冒険でもあるが、これこそ、クエスト・ガイドの醍醐味でもある。
むろん、命の危険もつきまとう。
だが、それを気にしていたら、この職業は勤まらない。
卯月とリタは遺書を事務に預けた。
もしもの時は、家族に届けるように、冒険に出る前には新しい遺書を書くのがこの職業では一般的な礼儀となっている。
今回は【卯月クエスト・ガイドオフィス】からクエスト・ガイド3名、【皐月パーティーズ】からクエスト・ガイド5名の合計8名による探索が予定されている。
効率の面からクエスト・ガイドは開拓冒険には2〜4名で出るのが一般的とされているので、8名というのは大人数という事になる。
今回訪れる未開の土地は調査カメラをあらかじめ20台送っていたが、いずれも映像が途中で途切れ、戻って来ていない。
確認されているだけでも3種類の危険生物がいることが解っている。
冒険者が遭遇するボスとして考えられているが、余りにも危険、人里に影響する様な状況になっていた場合、他の地へ誘導するか、最悪、排除の方向も視野に入れないといけない状況だった。
危険生物からそう遠くない距離に小さな町等が確認されたためだ。
そのあたりの確認作業も含めた遠方開拓冒険となる。
危険度は卯月達がこれまで冒険した開拓冒険とは比較にならないくらいアップしている。
これからは気を引き締めてかからないと行けない冒険が始まる。
「Xくん、リタさん、私、頑張るよ」
卯月は気持ちを奮い立たせた。
登場キャラクター説明
001 九歴 卯月(くれき うづき)

このお話の主人公。
幼馴染みの根角(ねずみ)の夢を引き継いでクエスト・ガイド(冒険案内人)を目指す女性。
6人姉妹の4女で他の5人は全て異母姉妹。
前向きなのは長所だが、注意力がいまいちたりず、おっちょこちょいでもある。
心情的な事に対してはかなり鈍い分類にはいる。
002 江藤 根角(えとう ねずみ)=審査官=X(エックス)君
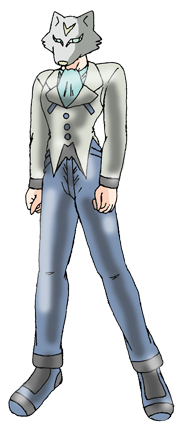
卯月の幼馴染みの青年。
卯月達6人姉妹の目標の存在でもある。
十八の時に行方をくらましている。
姿を隠して、姉妹の試験の審査官となりX(エックス)君として卯月の会社に入る。
006 九歴 弥生(くれき やよい)
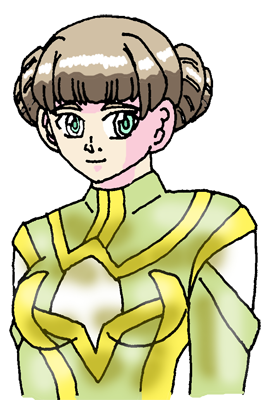
九歴6姉妹の三女で卯月の姉。
【弥生クエストカンパニー】の社長をしている。
世話好きでもあり、姉妹達を何気なくサポートしようとしていたりする。
会社の規模としては姉妹の中では、睦月の会社に次ぐ大所帯で、129名のクエスト・ガイドを社員にもつ。
Sランクを頂点として、続くAからCまでのランク付けをしている。
007 ミスターグッズ
天才的なアイテム職人。
彼の作るアイテムはひと味違うと評判だが、ちょっと変わり者で、特定のクエスト・ガイドオフィスと契約は交わしていない。
008 花巻 栞(はなまき しおり)
【弥生クエストカンパニー】のCランククエスト・ガイド。
組み手を苦手としている。
自信過剰な面があり、そのため、Cランクとなっている。
009 黒羽 聡美(くろばね さとみ)
【弥生クエストカンパニー】のCランククエスト・ガイド。
身体の大きいパワータイプ。
その分、小回りが利かない。
自分の非を認める潔さがある。
010 リタ・ウェーバー
【弥生クエストカンパニー】のCランククエスト・ガイド。
センスはあるのだが、好戦的なのが玉に瑕。
元、プロボクサー。
卯月との対戦後、【卯月クエスト・ガイドオフィス】に入社する。
011 ブリット・ウェーバー
事務スタッフとして、【卯月クエスト・ガイドオフィス】に入社した男性。
リタの従兄弟。
クエスト・ガイドの試験を優秀な成績でクリアするも、血を見ると失神するという致命的な欠点が見つかり、クエスト・ガイドの道から外れる。
リタの事が大好き。
012 スティーブ・ウェーバー
事務スタッフとして、【卯月クエスト・ガイドオフィス】に入社した男性。
リタの従兄弟で、ブリットの五つ年上の兄。
元、冒険者だったが、不注意からの事故で肩を壊し、冒険者としての道を断念。
ブリットの事を溺愛している。
リタから恋されているので、三角関係の様になっている。
013 皆川 彰人(みながわ あきと)
事務スタッフとして、【卯月クエスト・ガイドオフィス】に入社した少年。
が、正体はエンシェントドラゴンの魂を入れて蘇生させた死体。
月に一度、少年の両親に会いに行くという条件で、エンシェントドラゴンは彰人少年として、活動している。
本来、クエスト・ガイド志望だが、肉体が18才に育つまでは事務職という条件になっている。
見た目は子供でも幅広い知識を持つ。
014 桜咲 真尋(さくらざき まひろ)
事務スタッフとして、【卯月クエスト・ガイドオフィス】に入社した女性。
天才肌ではあるものの人間関係が上手く行かず、研究所を転々としていたのをXくんにスカウトされてやってきた。
A級クエスト・ガイドオフィスになれば研究所を割り当てて貰えるという条件で、入ってきた。
研究者と事務スタッフの二足のわらじでやっていく。